目次一覧
冴えない童貞 ~Sei教師と愛の祈り~
2話「モッコリ山の存在」
「…ふむふむ 」
「…なるほど 」
良太は相槌を打ち真面目に聖典を聞いているふりをしながらも、タンクトップの襟からチラッと見えるふっくらした胸元を覗き、その豊かな胸はどうなっているのだろうと、パンツの前開きから鬼棒が出してしまいそうなくらいタンクトップの中身を目に焼き付けていた。
しかし、とても目の保養になってとても良いものだが、もう暑さが限界。
今は一番日差しが強い昼下がりで、いつまでも外で話をしていたら熱中症になる。
聖書を読んでいる綺麗な女性も、先ほどから色っぽい胸元に大粒の汗をかいて止まらない。
「暑いですね」
良太はそう言って愛莉の顔を見た。
「はい。暑いですね…
毎日、暑くて嫌になっちゃいます」
宣教師の愛莉も釣られて暑さで赤くなった顔を見せながら返事を返した。
その赤ら顔に見える顔が、照れているような、火照っているような、何とも言えない色っぽい表情で、冴えない童貞の心にズキュンと刺さった。
「近所の目もあるし、外で話しているもの暑いですから」
やましい気持ちがあるわけではない。
いや、かなりあるが
「エアコンが効いて涼しい家内(なか)へ上がりませんか?
まだまだ続きが聞きたいし、このまま外で話をしていたら熱中症になってしまいますから」
と、人生初の冴えない男気を見せ、綺麗な女性を家の中へ招き入れようと試みる。
愛莉は猛暑の中、肌を焼くような陽射しを我慢して聖典を読んでいたから、良太の誘いがとても嬉しかった。でも、頭の隅にパンツのモッコリ山が残っている。
『もうおさまったかな…』
気付かれないようにチラッと下を見ると、まだ立派なモッコリ山のままだった。
とても休みたいけど、モッコリ山を平然と見せている男の家に上がったら何をされるか分からない。
「だ、大丈夫です。
暑さには、慣れていますから…」
と、滴る汗を我慢して丁寧に断るも
「いやいや、この猛暑では僕の方が熱中症になってしまいます」
と、良太が強引に手でも引いて家内へ入れようとする。
愛莉は手を振りながら
「大丈夫です!
大丈夫です!」
と断って見せたが、玄関の中に入ってしまった。
「ありがとうございます。
もう玄関の中で充分暑い陽射しが避けられますから、もう大丈夫です」
愛莉が遠慮深くそう言うも、玄関ではゆっくり胸元を目に焼き付けられないし、爆発した童貞心がそれ以上のことを望んで許さない。
「いやいや、綺麗な女性を玄関に立たせて、立ち話していたら、近所の人に笑われます。
どうぞ、どうぞ、家内(なか)へお上がりください。
何も無い家ですが、涼しいリビングにあがってゆっくり休んでください」
と少々強引に家内へ入れようとする。
愛莉はどうしようと迷いしながら家の中を覗くと、六人掛けのテーブルが玄関から見えた。
そこがリビングなのだろう。大きなテーブルがあるし、上がってもご家族が居れば安心かなと、玄関の靴や下駄箱を見回してみる。
どういう訳か、下駄箱には何足か入っているようだけど、良太のものと思われる靴が一足と、良太が今穿いていたサンダルだけしか出ていない。
あまりにも殺風景な玄関…。
ご家族は外出中なのだろうか。もし外出中なら、今この家には男一人ということになる。それは危険な目に合うことを承知して家に上がらなければならない。
他にご家族が居ないか、見える範囲で家内を見渡すもシーンと静まっていて、誰も居なさそうな感じがした。
先輩の宣教師から言われている『気を付けなさい』が身に沁みる。
良太は玄関の鍵を閉め、『これで』と下心を踊らせながら
「さぁ、こちらへどうぞ」
と、愛莉をリビングへ招く。
愛莉は危険を感じてこのまま帰ろうと思ったが、それでは今後の宣教師活動に支障が出るかも知れないし、久しぶりに宣教師の仕事が上手く出来たことも台無しになってしまう。だからと言って、リビングへ上がってしまえば、自ら危険を呼ぶことにもなる。
どうしようと迷った時、良太がリビングの扉から顔を覗かせ、早く上がってと急かして来た。
急かされた愛莉はどうしようにも無くなって、小声で「お邪魔します」と声をかけながら、夫へ『何か遇ったらごめんなさい』と恐る恐るリビングへ上がった。
リビングへ入って見れば、玄関同様、殺風景な広いリビングで生活感があまり感じられなかった。
大きな窓際には、大きなソファがあり、ソファのテーブルの上にはノートパソコンが置かれている。たぶん、そこで仕事か何かをしていたのだろう。
奥には殆ど使われていないと思われる立派なキッチンがあり、さっき玄関から見えていた六人掛けのテーブルがある。
愛莉がリビングをキョロキョロ見回して見ていると、良太がキッチンの奥から麦茶をデカンタごと持ってきて、氷一杯のグラスに麦茶を注ぎ、その一つを愛莉の前に置いて、まだ家中を見回している愛莉を大きなテーブルの真ん中に座らせた。
「外が暑かったから、中がひんやりするでしょう
良かったら、冷たい麦茶でもどうぞ」
良太がそう言って麦茶を差し出してくるが、世間では冷房の温度を上げて節電する風潮があるから、そこまでひんやりと冷えていない。どちらかと言うと、役所や公共施設などと同じくらいの室温で少し涼しいと感じるくらいだ。それでも、今まで強い日差し中、暑さを我慢して歩いていたから充分涼しく感じることができた。
それでTシャツとパンツだけの姿だったのかと夫の姿を思い出し、ひとまず納得した。
「いただきます」
麦茶を一口いただきながら、モッコリ山じゃなかったら真面目な人なのかも、と深く座り直す。
人知れず愛莉が警戒している中、生まれて初めて家に女性を招き入れることが出来た良太は、麦茶を差し出しながらも、興奮と緊張で体が震えそうになっていた。
現実の女性はトレーニング映像のようにいかない。
心が赴くまま広いリビングへ招くことは出来たが、綺麗な女性と二人きりになることなど、今までの人生の中でない。ましてや、女性に対するスキルが皆無と言うこともあって、これから先どう接したら良いのか、分からなくなって黙り込んでしまった。
そんな中、緊張と興奮が高まり切羽詰まって、ふっくら膨らんでいる胸元へ惹かれるように愛莉の隣へ着席してしまう。だが、下心を見せるわけには行かない。
気持ちを落ち着かせて冷静さを取り戻すため、麦茶をグビグビ一気に飲み干した。
「ふぅ~、冷たくて美味しい…
え~と…
すみません。お名前をど忘れしてしまいました。
もう一度、お名前を聞いてもよろしいですか?」
愛莉は、麦茶を一気飲みする良太を見て、それほど外が暑かったのかと思ったが、それとモッコリ山を隠さず隣に座るのは別の話。どうして、何も穿かず隣に座ったのかは謎だけど、良太は家人で、愛莉は客人となる。家人が家ですることは、客人には何も言えないし、今さっき出会ったばかりだから失礼なことは言えない。
危険度が跳ね上がる中、自ら危険を呼ぶ言動は避けたい。
「いきなり来たから、忘れるのも当然ですよね。
私の名前は桃木愛莉と申します。
桃木はもものきと書いて、あいは愛の字、りは莉の字です。莉の字の説明ができなくてごめんなさい」
愛莉は隣に座った良太をより一層警戒心しながらも、いつもと同じように愛嬌ある口調で話をしてニコッと微笑んで見せた。
その愛嬌ある微笑みを、良太は真面目な顔してジッと見つめ返す。
「莉の字は、字を見ればわかります…
ももきあいりさん…
ももきあいりさん…
ももきあいりさん…
はい! ももきあいりさん! 覚えました!
桃木さんと呼んで良いですか?」
名前を呪文のように連呼され、変な事になったかなと不安がって見せると、良太もニヤッと微笑んで見せた。
その微笑みがどこか嫌らしい。
反射的に体を背けてしまったが、良太がまだジッと顔を覗き込んでくる。
そんなに嫌らしい目で見つめられると、目のやり場を無くし、どこを見れば良いのか困ってしまう。その反面、好みのイケメンがジッと見つめてくるから、女心がドキドキときめく。
「桃木さん。まだ顔が赤いようですね。
外が暑かったから、なかなか体が冷えないのでしょう。
まだ熱くて汗が止まらないなら、上着を脱いで涼しんでも良いですよ。
どうぞ、遠慮なされずに上着を脱いで休んでください」
良太がそう言ってスッと立ち上がり、目をキョロキョロ泳がせて挙動不審になっている愛莉のカーディガンに手をかける。
愛莉は日焼けしないようにカーディガンを着ていたのもあるが、見ず知らずのお宅を訪問して宣教活動するため、なるべく肌の露出は避けていた。そのカーディガンを脱がされると、下は肌の露出が増えるタンクトップ。
いくら好みのイケメンだろうと肌を見せるのは避けたい。そして、モッコリ山を喜ばせることにもなる。さらに危険度が増すと言うものだ。
「だ、大丈夫です。
充分涼しいですし、ご家族さんもいるだろうし、カーディガンを脱がなくても、充分涼しいですから」
「まぁまぁ、遠慮なされずに。
顔が赤いですから…」
愛莉が警戒心を強めて嫌がって見せるも、すんなり肩からカーディガンを脱がされた。
愛莉は心のどこかでドキドキ何かを期待していた。
それは、先輩の女宣教師から『女一人で宣教活動をする時は気を付けない』と言われていたのだけど、『旦那には内緒だけど、女としておいしい想いもすることがあるから…』と真逆のことを言われていたのだ。
数々のお宅を訪問していれば、稀にタイプの男性と出会うこともあり、いつしか女宣教師の『おいしい想いもするから』が理解できるようになり、夫には絶対言えないふしだらな想像をすることもあったからだ。
「どうです? 上着を脱ぐと涼しいでしょう?」
緊張で震える手を我慢してカーディガンを脱がして見れば、タンクトップが女性らしい丸みを帯びた細い肉体にぴったりしていて、形が良い豊かな胸がくっきり浮かび上がっている。
その豊潤な聖乳を覗きたいと、荒くなる鼻息を静まらせながらタンクトップの襟をの覗いてみるも、愛莉は欲望むき出しの視線を感じ取ったのか、こちらの顔をチラッと見て、刺激的な谷間を覗かせてくれない。
良太は、チラ見しているのがバレてしまうのを恐れて平静さを装い、真面目な顔を続けた。
「はい。そうですね…」
カーディガンを脱がされて見れば、充分涼しいと感じることができた。
改めて『なるほど』と思ったが、夫以外の男の前では肌の露出を控えている。心の奥でときめきを期待しているところもあるが、取り返しのつかないことになってからでは手遅れになる。しっかり気を引き締めて警戒心を強めた。
「さぁ、涼しくなったところで、さっきの続きを話しましょう」
モッコリ山を隠さずに良太がそう言って、本来の目的であるキリス秘宝教の教えを聞いてくる。
モッコリ山じゃなかったら良いことなのだけど、何も手を出して来ないか間を置く。
ご家族が外出中なら、そのうち帰ってくるだろうし、家族ごと入信させられることが出来るかも知れない。
「そう言えば、私もご主人の名前をお伺いしていなかったですよね。
もし、お良しければ、お名前を聞いてもよろしいですか?」
愛莉は、本来の目的を始める前に、良太の身辺を少し探ってみることにした。
「いや~、ご主人なんて~。
俺、こう見えても独身なんですよ。結婚しているように見えました?
まぁ、ずっと冴えないから独身なんですけど…
この家は新しく見えても、親の遺産で俺が建てた訳ではないですよ」
「そうなんですか。
でも、男前で家持ちなら女性は喜びますよ」
「いやいや、そんなにおだてなくとも… 俺、何も持っていないから何も出せないですよ。アハハ…
俺はこの家で寂しく独り暮らししている“さえきりょうた”です。
漢字で書くと、冴木良太です。
字で見ると、冴えないのだか、良好なのだか、名前からして矛盾しているように思えて、嫌になってしまいます」
ずっとモッコリ山なのに話方や顔が真面目。
その真面目さから、つい警戒が緩んで良太の方に身体を向けてしまった。
『あっ!』
夫のものより遥かに大きいのは見てわかるけど、そんなに自信があるのだろうか。
「そんな冴えないなんて、こんなに立派なモノ… あっ、モノじゃなくて家…
立派な家があるから、彼女さんが可哀想ですよ。
え~と、冴木さんってお呼びしてもよろしいですか?」
「はい。良太でも良いですけど…
今日、初めてお会いした人に良太と言って、と言うもの可笑しいですから冴木で良いです。
それと彼女はいません。彼女が出来ない冴えない独身です」
良太は鬼棒をビンビン起たせたまま、綺麗な女性と会話できる喜びと緊張で聞いていないことをベラベラしゃべり出し、綺麗な女性に名前を呼んでもらえたことに喜びを覚え、色っぽい胸元を目に焼き付けていた。
愛莉はモッコリ山を気に掛けながら、この家には良太以外誰も住んでいないこと確認できたので、さらに警戒を強くすると共に、大きな家で二人きりという状況が心の奥で期待感を膨れ上がらせた。
不安と期待が揺れ動く中、良太にも見えるよう聖典をテーブルの上に置き、聖典の話を読み聞かせ始めた。
目次へ戻る
冴えない童貞 ~Sei教師と愛の祈り~
2話「モッコリ山の存在」
「…ふむふむ 」
「…なるほど 」
良太は相槌を打ち真面目に聖典を聞いているふりをしながらも、タンクトップの襟からチラッと見えるふっくらした胸元を覗き、その豊かな胸はどうなっているのだろうと、パンツの前開きから鬼棒が出してしまいそうなくらいタンクトップの中身を目に焼き付けていた。
しかし、とても目の保養になってとても良いものだが、もう暑さが限界。
今は一番日差しが強い昼下がりで、いつまでも外で話をしていたら熱中症になる。
聖書を読んでいる綺麗な女性も、先ほどから色っぽい胸元に大粒の汗をかいて止まらない。
「暑いですね」
良太はそう言って愛莉の顔を見た。
「はい。暑いですね…
毎日、暑くて嫌になっちゃいます」
宣教師の愛莉も釣られて暑さで赤くなった顔を見せながら返事を返した。
その赤ら顔に見える顔が、照れているような、火照っているような、何とも言えない色っぽい表情で、冴えない童貞の心にズキュンと刺さった。
「近所の目もあるし、外で話しているもの暑いですから」
やましい気持ちがあるわけではない。
いや、かなりあるが
「エアコンが効いて涼しい家内(なか)へ上がりませんか?
まだまだ続きが聞きたいし、このまま外で話をしていたら熱中症になってしまいますから」
と、人生初の冴えない男気を見せ、綺麗な女性を家の中へ招き入れようと試みる。
愛莉は猛暑の中、肌を焼くような陽射しを我慢して聖典を読んでいたから、良太の誘いがとても嬉しかった。でも、頭の隅にパンツのモッコリ山が残っている。
『もうおさまったかな…』
気付かれないようにチラッと下を見ると、まだ立派なモッコリ山のままだった。
とても休みたいけど、モッコリ山を平然と見せている男の家に上がったら何をされるか分からない。
「だ、大丈夫です。
暑さには、慣れていますから…」
と、滴る汗を我慢して丁寧に断るも
「いやいや、この猛暑では僕の方が熱中症になってしまいます」
と、良太が強引に手でも引いて家内へ入れようとする。
愛莉は手を振りながら
「大丈夫です!
大丈夫です!」
と断って見せたが、玄関の中に入ってしまった。
「ありがとうございます。
もう玄関の中で充分暑い陽射しが避けられますから、もう大丈夫です」
愛莉が遠慮深くそう言うも、玄関ではゆっくり胸元を目に焼き付けられないし、爆発した童貞心がそれ以上のことを望んで許さない。
「いやいや、綺麗な女性を玄関に立たせて、立ち話していたら、近所の人に笑われます。
どうぞ、どうぞ、家内(なか)へお上がりください。
何も無い家ですが、涼しいリビングにあがってゆっくり休んでください」
と少々強引に家内へ入れようとする。
愛莉はどうしようと迷いしながら家の中を覗くと、六人掛けのテーブルが玄関から見えた。
そこがリビングなのだろう。大きなテーブルがあるし、上がってもご家族が居れば安心かなと、玄関の靴や下駄箱を見回してみる。
どういう訳か、下駄箱には何足か入っているようだけど、良太のものと思われる靴が一足と、良太が今穿いていたサンダルだけしか出ていない。
あまりにも殺風景な玄関…。
ご家族は外出中なのだろうか。もし外出中なら、今この家には男一人ということになる。それは危険な目に合うことを承知して家に上がらなければならない。
他にご家族が居ないか、見える範囲で家内を見渡すもシーンと静まっていて、誰も居なさそうな感じがした。
先輩の宣教師から言われている『気を付けなさい』が身に沁みる。
良太は玄関の鍵を閉め、『これで』と下心を踊らせながら
「さぁ、こちらへどうぞ」
と、愛莉をリビングへ招く。
愛莉は危険を感じてこのまま帰ろうと思ったが、それでは今後の宣教師活動に支障が出るかも知れないし、久しぶりに宣教師の仕事が上手く出来たことも台無しになってしまう。だからと言って、リビングへ上がってしまえば、自ら危険を呼ぶことにもなる。
どうしようと迷った時、良太がリビングの扉から顔を覗かせ、早く上がってと急かして来た。
急かされた愛莉はどうしようにも無くなって、小声で「お邪魔します」と声をかけながら、夫へ『何か遇ったらごめんなさい』と恐る恐るリビングへ上がった。
リビングへ入って見れば、玄関同様、殺風景な広いリビングで生活感があまり感じられなかった。
大きな窓際には、大きなソファがあり、ソファのテーブルの上にはノートパソコンが置かれている。たぶん、そこで仕事か何かをしていたのだろう。
奥には殆ど使われていないと思われる立派なキッチンがあり、さっき玄関から見えていた六人掛けのテーブルがある。
愛莉がリビングをキョロキョロ見回して見ていると、良太がキッチンの奥から麦茶をデカンタごと持ってきて、氷一杯のグラスに麦茶を注ぎ、その一つを愛莉の前に置いて、まだ家中を見回している愛莉を大きなテーブルの真ん中に座らせた。
「外が暑かったから、中がひんやりするでしょう
良かったら、冷たい麦茶でもどうぞ」
良太がそう言って麦茶を差し出してくるが、世間では冷房の温度を上げて節電する風潮があるから、そこまでひんやりと冷えていない。どちらかと言うと、役所や公共施設などと同じくらいの室温で少し涼しいと感じるくらいだ。それでも、今まで強い日差し中、暑さを我慢して歩いていたから充分涼しく感じることができた。
それでTシャツとパンツだけの姿だったのかと夫の姿を思い出し、ひとまず納得した。
「いただきます」
麦茶を一口いただきながら、モッコリ山じゃなかったら真面目な人なのかも、と深く座り直す。
人知れず愛莉が警戒している中、生まれて初めて家に女性を招き入れることが出来た良太は、麦茶を差し出しながらも、興奮と緊張で体が震えそうになっていた。
現実の女性はトレーニング映像のようにいかない。
心が赴くまま広いリビングへ招くことは出来たが、綺麗な女性と二人きりになることなど、今までの人生の中でない。ましてや、女性に対するスキルが皆無と言うこともあって、これから先どう接したら良いのか、分からなくなって黙り込んでしまった。
そんな中、緊張と興奮が高まり切羽詰まって、ふっくら膨らんでいる胸元へ惹かれるように愛莉の隣へ着席してしまう。だが、下心を見せるわけには行かない。
気持ちを落ち着かせて冷静さを取り戻すため、麦茶をグビグビ一気に飲み干した。
「ふぅ~、冷たくて美味しい…
え~と…
すみません。お名前をど忘れしてしまいました。
もう一度、お名前を聞いてもよろしいですか?」
愛莉は、麦茶を一気飲みする良太を見て、それほど外が暑かったのかと思ったが、それとモッコリ山を隠さず隣に座るのは別の話。どうして、何も穿かず隣に座ったのかは謎だけど、良太は家人で、愛莉は客人となる。家人が家ですることは、客人には何も言えないし、今さっき出会ったばかりだから失礼なことは言えない。
危険度が跳ね上がる中、自ら危険を呼ぶ言動は避けたい。
「いきなり来たから、忘れるのも当然ですよね。
私の名前は桃木愛莉と申します。
桃木はもものきと書いて、あいは愛の字、りは莉の字です。莉の字の説明ができなくてごめんなさい」
愛莉は隣に座った良太をより一層警戒心しながらも、いつもと同じように愛嬌ある口調で話をしてニコッと微笑んで見せた。
その愛嬌ある微笑みを、良太は真面目な顔してジッと見つめ返す。
「莉の字は、字を見ればわかります…
ももきあいりさん…
ももきあいりさん…
ももきあいりさん…
はい! ももきあいりさん! 覚えました!
桃木さんと呼んで良いですか?」
名前を呪文のように連呼され、変な事になったかなと不安がって見せると、良太もニヤッと微笑んで見せた。
その微笑みがどこか嫌らしい。
反射的に体を背けてしまったが、良太がまだジッと顔を覗き込んでくる。
そんなに嫌らしい目で見つめられると、目のやり場を無くし、どこを見れば良いのか困ってしまう。その反面、好みのイケメンがジッと見つめてくるから、女心がドキドキときめく。
「桃木さん。まだ顔が赤いようですね。
外が暑かったから、なかなか体が冷えないのでしょう。
まだ熱くて汗が止まらないなら、上着を脱いで涼しんでも良いですよ。
どうぞ、遠慮なされずに上着を脱いで休んでください」
良太がそう言ってスッと立ち上がり、目をキョロキョロ泳がせて挙動不審になっている愛莉のカーディガンに手をかける。
愛莉は日焼けしないようにカーディガンを着ていたのもあるが、見ず知らずのお宅を訪問して宣教活動するため、なるべく肌の露出は避けていた。そのカーディガンを脱がされると、下は肌の露出が増えるタンクトップ。
いくら好みのイケメンだろうと肌を見せるのは避けたい。そして、モッコリ山を喜ばせることにもなる。さらに危険度が増すと言うものだ。
「だ、大丈夫です。
充分涼しいですし、ご家族さんもいるだろうし、カーディガンを脱がなくても、充分涼しいですから」
「まぁまぁ、遠慮なされずに。
顔が赤いですから…」
愛莉が警戒心を強めて嫌がって見せるも、すんなり肩からカーディガンを脱がされた。
愛莉は心のどこかでドキドキ何かを期待していた。
それは、先輩の女宣教師から『女一人で宣教活動をする時は気を付けない』と言われていたのだけど、『旦那には内緒だけど、女としておいしい想いもすることがあるから…』と真逆のことを言われていたのだ。
数々のお宅を訪問していれば、稀にタイプの男性と出会うこともあり、いつしか女宣教師の『おいしい想いもするから』が理解できるようになり、夫には絶対言えないふしだらな想像をすることもあったからだ。
「どうです? 上着を脱ぐと涼しいでしょう?」
緊張で震える手を我慢してカーディガンを脱がして見れば、タンクトップが女性らしい丸みを帯びた細い肉体にぴったりしていて、形が良い豊かな胸がくっきり浮かび上がっている。
その豊潤な聖乳を覗きたいと、荒くなる鼻息を静まらせながらタンクトップの襟をの覗いてみるも、愛莉は欲望むき出しの視線を感じ取ったのか、こちらの顔をチラッと見て、刺激的な谷間を覗かせてくれない。
良太は、チラ見しているのがバレてしまうのを恐れて平静さを装い、真面目な顔を続けた。
「はい。そうですね…」
カーディガンを脱がされて見れば、充分涼しいと感じることができた。
改めて『なるほど』と思ったが、夫以外の男の前では肌の露出を控えている。心の奥でときめきを期待しているところもあるが、取り返しのつかないことになってからでは手遅れになる。しっかり気を引き締めて警戒心を強めた。
「さぁ、涼しくなったところで、さっきの続きを話しましょう」
モッコリ山を隠さずに良太がそう言って、本来の目的であるキリス秘宝教の教えを聞いてくる。
モッコリ山じゃなかったら良いことなのだけど、何も手を出して来ないか間を置く。
ご家族が外出中なら、そのうち帰ってくるだろうし、家族ごと入信させられることが出来るかも知れない。
「そう言えば、私もご主人の名前をお伺いしていなかったですよね。
もし、お良しければ、お名前を聞いてもよろしいですか?」
愛莉は、本来の目的を始める前に、良太の身辺を少し探ってみることにした。
「いや~、ご主人なんて~。
俺、こう見えても独身なんですよ。結婚しているように見えました?
まぁ、ずっと冴えないから独身なんですけど…
この家は新しく見えても、親の遺産で俺が建てた訳ではないですよ」
「そうなんですか。
でも、男前で家持ちなら女性は喜びますよ」
「いやいや、そんなにおだてなくとも… 俺、何も持っていないから何も出せないですよ。アハハ…
俺はこの家で寂しく独り暮らししている“さえきりょうた”です。
漢字で書くと、冴木良太です。
字で見ると、冴えないのだか、良好なのだか、名前からして矛盾しているように思えて、嫌になってしまいます」
ずっとモッコリ山なのに話方や顔が真面目。
その真面目さから、つい警戒が緩んで良太の方に身体を向けてしまった。
『あっ!』
夫のものより遥かに大きいのは見てわかるけど、そんなに自信があるのだろうか。
「そんな冴えないなんて、こんなに立派なモノ… あっ、モノじゃなくて家…
立派な家があるから、彼女さんが可哀想ですよ。
え~と、冴木さんってお呼びしてもよろしいですか?」
「はい。良太でも良いですけど…
今日、初めてお会いした人に良太と言って、と言うもの可笑しいですから冴木で良いです。
それと彼女はいません。彼女が出来ない冴えない独身です」
良太は鬼棒をビンビン起たせたまま、綺麗な女性と会話できる喜びと緊張で聞いていないことをベラベラしゃべり出し、綺麗な女性に名前を呼んでもらえたことに喜びを覚え、色っぽい胸元を目に焼き付けていた。
愛莉はモッコリ山を気に掛けながら、この家には良太以外誰も住んでいないこと確認できたので、さらに警戒を強くすると共に、大きな家で二人きりという状況が心の奥で期待感を膨れ上がらせた。
不安と期待が揺れ動く中、良太にも見えるよう聖典をテーブルの上に置き、聖典の話を読み聞かせ始めた。
目次へ戻る

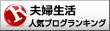


コメント